今、こちら(ほんわか倶楽部)の傾聴活動に関するメール講座の中でも外部講師の方により述べられているのですが、傾聴を学んでも出来るようになりにくい人の特徴の1つとして、「カウンセラー(自分)の方が偉い(正しい・勉強している)と思っている」人…ということが挙げられています。
この言葉を聞いた時「世間にはいるなぁ…」と、私自身のクライエント経験で色々なところで話ししてきた時や、他、傾聴メンバー新規募集で、実にたくさんの多種多様な方々と話ししてきた際にも…残念ながら一部の方に感じてきたことを思い出しました。
(このことは過去記事『「聴いてあげます」・「聴かせていただきます」』でも少し触れたことがあります)。
ご本人の経験値や知見などで視えてくるものがあるんでしょうが、傾聴が必要とされる場面では、そういうことじゃないんですよね…。
なぜ、無条件の肯定的配慮(積極的関心)で共感的に寄り添って聴いてもらうことが重要なのか、それが痛切に必要な状態とは、どういうものなのか…
そこが理屈(頭)ではなく…なんども何度も心で腑に落ちていれば、ジャッジする感覚は自然と横に置いておけたり、正論だけで考えてしまうことも置いておけるようになると、私には思えています。
分かったような気になるのではなくて、何度も何度も、深く強く実感すればするほど、リアルの現場では自然と反映できます。
そもそも「誰にも言えなかった。言っても聴いてもらえないと痛感してきたような胸の内を…どこか、上から目線で接してくる相手に本心を言えるものか!」と、私なら思ってしまいそうです。
聞き手にジャッジされる、批判される、先入観や固定観念のバイアス(フィルター、色眼鏡)にかけられるなどと感じると、はなはだ話しづらくストレス過多となって、しまいに話せなくなってしまいます。
私自身、クライエントとして話ししていた時、「私(村田)は、聞き手さんの先入観、固定観念を自己満足させるために存在しているのではないし、心の内を明かしているのでもない」ということも感じてきました。
傾聴を学んでも出来るようになりにくい人の、もう1つの特徴「そもそもの動機がカウンセラー(自分)の利益のためである」ということにも繋がることですね。心の利益(利得)というのもあります。
もし、聞き手の自己満足(承認欲求など)のため”だけ”に、辛い状態にある話し手の心を聞こうとして、存在を都合よく消費するのでしたら、とんでもないことと私は思います。
傾聴の場なのに、聞き手にとっての何らかの利得を得るために、お相手に向けた「感情が置いてきぼりになっている」としたら、どうなんでしょう?
私は傾聴の仕事以外も多々していますし、小規模ながらも起業家であり経営者です。
傾聴以外の仕事(ビジネスシーン)では、時にはお互いに感情を一時的に置いておく必要も出てきますし、逆に感情を置いて自己不一致では進められない時、その両方があります。
ビジネスの場では、そりゃ、そういう必要も時にはあるでしょう。
ですが、それでもやっぱり人は人なんです。
常に、心を持っているのは言うまでもないことです。
日々、様々な起業家・経営者の方々と交流することがありますが、それでもやはり傾聴マインドを使っているときと、そうでない時には物事が心地よく進むスムーズさ・深さに違いがあります。
その違いもまた表面的なところだけを聞くのではなく、本質的なところに耳を傾けていこうとするほどに、相手の心に伝わるのだなと感じてきました。
このことはプライベートでも充分に言えることです。
これら感じたことを書き出すと、まだまだ沢山あるのですがキリがなくなってしまいますので、機会があればお話できましたら幸いです。
拙文を綴りましたが、ご精読いただきまして、ありがとうございます。

ネイティブ・アメリカンの有名な言葉からー
「あなたが生まれたとき、周りの人は笑って、あなたは泣いていたでしょう。だから、あなたが死ぬときは、あなたが笑って、周りの人が泣くような人生をおくりなさい」
少しでも、このように生きたいね^^
~ 親愛なる娘へ
きみが生まれてきてくれた時のこと、思い出さない日は本当にないよ。
涙が出て止まらなかった、あの時…。



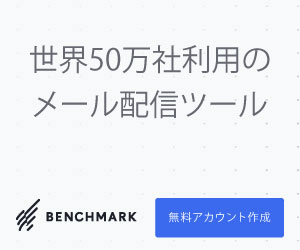
コメント